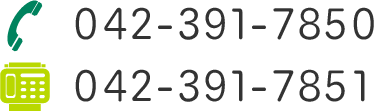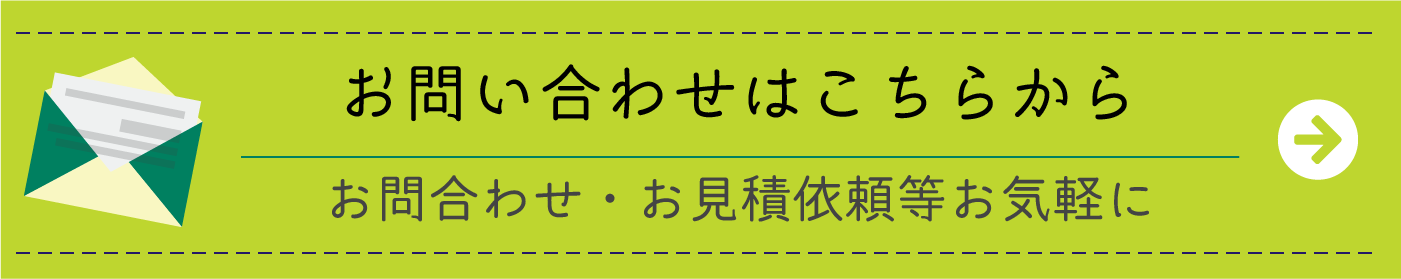雨量計とは?
雨量をはかる大切さ
雨量を測定することは、防災の観点から非常に重要です。日本各地で毎年のように河川の氾濫や土砂災害が発生し、大きな被害を与えています。近年では都市部でのゲリラ豪雨も増えており、雨による被害は甚大なものとなることがあります。それらを未然に防いだり、被害を最小限に食い止めるために雨量計が活用され、雨量を正確に把握することは防災や生活に欠かせなくなっています。
雨量は「一定の時間にどれくらいの水が降ったか」を示し、mm(ミリメートル) で表します。雨量1mmとは、1平方メートルの面積に1リットルの水が降り注いだ量です。1時間で1mmなら小雨、20mmを超えると大雨注意報が出る目安になります。
もっと雨量計のことを知りたい方には、次の記事もお薦めです。
雨量計の仕組み
降った雨の量を計測する装置が「雨量計」です。
上部の受水器(漏斗状の入水口)で雨水を集め、その量を計測します。寒冷地では雪や氷で観測が妨げられないよう、ヒーター付きのタイプも用いられています。
雨量計には大きく2つの種類があります。
● 貯水型雨量計
雨水を容器にため、その量を測るシンプルな方式。構造が簡単で低コストですが、自動排水ができないため主に有人観測に使われます。
● 転倒ます型雨量計
「転倒ます」と呼ばれる小さな容器で雨を受け、一定量がたまるとシーソーのように転倒して排水。この回数をカウントすることで降水量を記録します。自記電接計数器やデータロガーなどをつければ長期間の稼働による自動連続観測が可能となるほか、遠隔地の無人モニタリングなども可能となります。そのため日本国内の観測システムには、気象庁をはじめ転倒ます型が中心となって導入されています。また、気象業務法により防災目的や公的な気象観測に使用されるものは、気象庁検定に合格した転倒ます型雨量計を用いることが定められています。
雨量計の種類については、次の記事も参考になさってください。
地上の雨量計に加え、レーダーで降水の分布を観測する方法もあります。広範囲の雨の様子を把握できますが、誤差も生じやすいため、実際には雨量計のデータで補正した「解析雨量」が活用されています。
設置のポイント
正確な計測には、設置環境も重要です。
● 建物や樹木から離す(風の乱れを避ける)
● 地面からの雨の跳ね返りを防止するため、芝生の上に設置する
● 寒冷地では、凍結防止や積雪に対応した工夫をする
こうした配慮によって、安定して正確なデータを得ることが可能になります。
雨量計の活用
雨量計は天気予報のためだけでなく、
● 防災(洪水・土砂災害の監視)
● ダムや河川の管理
● 農業や土木建築での水利用管理
など幅広い分野で活用されています。近年ではリアルタイム監視システムと連携し、集中豪雨による被害を最小限に抑えるためにも役立っています。
雨量計の使い方や活用方法をもっと知りたい方には、次の記事もお薦めです。