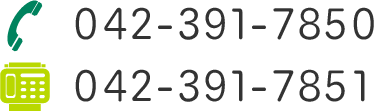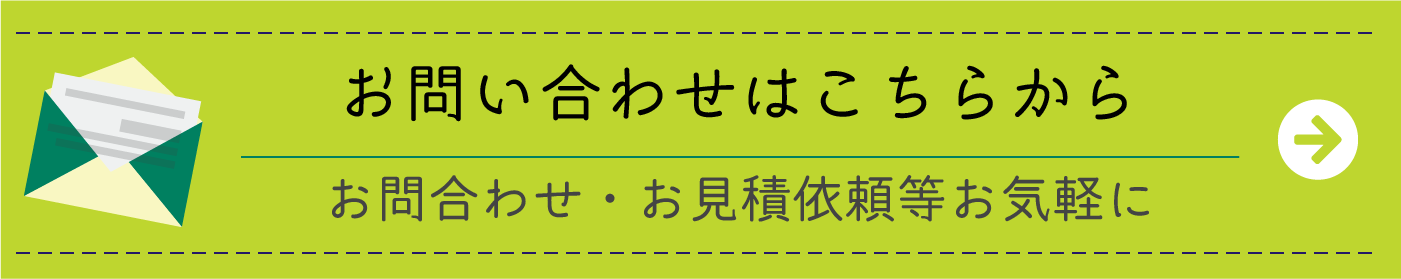暑さ指数(WBGT)とは?
2025-05-20
暑さ指数(WBGT)は、熱中症の危険度を判断する目安となる指標で、”熱中症指数”と呼ばれることもあります。1954年にアメリカで提案された指標で、熱中症を未然に防ぐことを目的として国際的に用いられています。
WBGTは乾球温度(気温)、湿球温度(気温と湿度)、黒球温度計(輻射熱などに関係する温度)の3種類を計測して算出されることから「湿球黒球温度」と言われ、英語表現のWet Bulb Globe Temperatureの頭文字をとって「WBGT」と略称で呼ばれることもあります。
単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とはかなり異なり、人体が感じる熱を表すので、熱中症の危険度を表す指標となります。
暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、気温を取り入れた指標です。
日常生活では暑さ指数(WBGT)が28℃を超えると熱中症の危険性が一気に高まります。一般的に気温が高くなると熱中症になりやすくなりますが、気温はそれほど高くなくとも湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、つまり体の熱が逃げにくくなるため、熱中症のリスクが高まります。
真夏になるとニュース等で「最高気温が〇〇度を記録した」とか、「熱中症で〇〇人搬送された」というようなことを耳にすることが多くなります。ニュースや天気予報で“最高気温”に注目してしまいがちですが、気温だけを見て熱中症に備えようとすると湿度や換気などへの注意がおろそかになってしまいます。猛暑日ではないからと油断すると、危険な状態に陥る可能性が十分にあります。外出や屋内外で作業をする時には「暑さ指数(WBGT)」を活用した対策をすると良いでしょう。
2025年6月1日からは労働安全衛生規則の改正が施行され、事業者に対して熱中症対策が義務付けられます。熱中症のリスクを知るためには、暑さ指数(WBGT値)を正しく測定・評価することが重要です。そのために、JIS規格(JIS Z 8504またはJIS B 7922)に適合した計測器を用いることが求められています。気象庁や環境省が発表するWBGT値は、地域全体の代表値であり、参考にはなりますが、実際の作業環境の状況とは大きく異なる可能性があります。作業現場ごとに個別にWBGT値を測定することで、より実態に即した対策を講じることができ、安全管理の精度が高まります。